 |

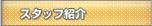

皆さん
お元気ですか!
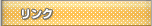
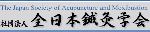

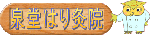
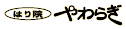

このHPに掲載されている
器具の写真撮影を
お願いしました

このHPは
ホームページ・ビルダー9で
製作しました


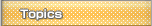
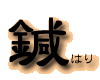


|
 |
 |
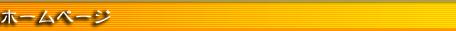 |
 |
 |
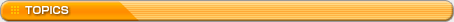 |
 |
 |
 |
 |
| |
 |
鍼灸(しんきゅう)治療の「はり」とは  |
| |
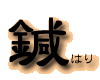 はりを表すのに古くは鍼(ハリ・シン)の字が使われてきました。 はりを表すのに古くは鍼(ハリ・シン)の字が使われてきました。
最近では針(ハリ・シン)を使う事も多くなってきましたが、金ヘンに十の針は、「先のとがった一本の細いもの」という意味で、縫い針や釣り針などを表します。
それに対しはり治療の鍼は金ヘンに咸からなります。
咸は「刃物で刺激を加えて邪気を封じる」という意味で、鍼は「とがった石で身体を刺激し病を封じる」という意味です。鍼は、針とは違い病気を治療するための道具をさす字なのです。
また、これは私の私論ですが咸は感じるという字からも来ているのではないかと、思うのです。 実際臨床上、気の調整をする鍼をツボにあてていますと敏感な患者さんですと、経絡(気の流れる道)にそって“ひびき”を感じたり、患部に対して心地よい“ひびき”を感じる方が多々見えます。 この“ひびき”はズキンとひびく感覚とは明らかに違い、心地良い“ひびき”なのです。 この様な体験から鍼という字が考えられ治療用のはりにあてられたのではないかと、私は思っています。
ですから当院では鍼の字にこだわり、その字にこめられた意味を大切にし、心地よい鍼治療を目指して日夜研鑚しています。
|
|
|
 |
脈診流経絡治療とは?  |
| |
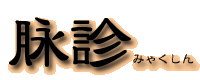 まず、患者さんの左右の手首の脈を診ます。運動や緊張によって脈の状態が変わるように、人それぞれ脈の状態が体調・症状などによって変わります。脈は体のデータ―ベースのようなものです。これを脈診と言います。 まず、患者さんの左右の手首の脈を診ます。運動や緊張によって脈の状態が変わるように、人それぞれ脈の状態が体調・症状などによって変わります。脈は体のデータ―ベースのようなものです。これを脈診と言います。
それに加え皮膚や腹部の状態を拝見し(触診・腹診)、一人一人の体質・体力・全身の状態を充分に把握します。その上で東洋医学独特の法則に従い、ツボを選び、鍼をして、体全体の機能的アンバランスを調整します。
これにより、人間が本来持つ自然治癒力を最高度に発揮させ、且つ高めていく治療法です。決して、その場限りの痛みを止めるだけの治療ではありません。 治療の効果も、直後だけではなく、一晩寝た後にも出てきます。
 |
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
| |
 |
お血(おけつ)と言う考え方  |
| |
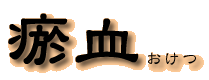 お血とは、東洋医学独特の病理観で、血液が汚れドロドロになって、スムーズに流れなくなり滞っている病的な血液を言います お血とは、東洋医学独特の病理観で、血液が汚れドロドロになって、スムーズに流れなくなり滞っている病的な血液を言います
お血とは、血液の流れが緩慢になって臓腑や経絡内に停滞した物質、および経脉から離れた血液(いわゆる内出血に相当するもの)が消散、あるいは排泄されずに滞留した物質の総称です。そしてお血が形成されると、正常な血液のもつ濡養作用(全身を栄養し潤す作用)が減退するほか、血液の運行が影響されて疼痛や出血あるいは腫魂などが出現します。
(やさしい中医学入門より)
お血という概念は現代医学にはない東洋医学独特の病理観であり多くの治りにくい病気に深く関与していることが多いです。
お血の『お』は「ふさがる」、「血のとどこおる病気」の意味がある。「漢和辞典」では、「血液の循環が悪くなって起こる病気」、「古血」、「流れずにとどこおっている血液」と説明されています。
『広辞苑』では「古くなった血」とあります。お血の『お』は「淤」に由来するようで、淤には「泥が沈殿してふさがる」意味があるので、“さんずいへん”を“やまいだれ”に変え、血の病症を意味する言葉に転用したものであると言われています。
現代語として死語に近いですが、古くからお血は、他にもいろいろな別名で呼ばれていたようです。蓄血・留血・積血・敗血・悪血・古血などです。
このようにその由来を辿ってみると、先人は「古い、流れない血液は身体に災いを来すらしい」と認識していたようです。お血は、血液の流れが緩やかになって臓腑や経絡に停滞すると生じます。つまり古い血液が澱んでいる状態と、それによって起こる色々な症状を言っています。
(医道の日本 通巻684号 お血 西田皓一より)

|
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
|
 |